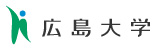研究所セミナーのお知らせ
下記の日程でセミナーを行います.多数の参加をお待ちしております<(_ _)>
お問い合わせは,ナノデバイス・バイオ融合科学研究所(学内内線6265)まで.
Recent
- セミナー案内
Ⅲ-Ⅳ-Ⅴ族半導体デバイス 若手の会 第2回 勉強会
広島大学の半導体デバイス・プロセスの若手研究者の互いの研究の理解、研究交流、議論の場として、Ⅲ-Ⅳ-Ⅴ族半導体デバイス 若手の会 勉強会を開催いたします。第2回として、ナノデバイス・バイオ融合科学研究所・黒木が、多結晶シリコン薄膜トランジスタ研究について結晶状態・デバイス特性等の話題提供のもと、議論を行います。ご興味のある方はご参加ください。- 日時:平成25年4月26日(金) 18:00-20:00
- 場所:先端物質科学研究科 402A 会議室
- 発表:黒木伸一郎(ナノデバイス・バイオ融合科学研究所)
- 題目:「連続発振レーザによるシリコン薄膜結晶化と、シリコン薄膜トランジスタ」
- 世話人:
村上 秀樹(内線:7468)、花房 宏明(内線:7468)、富永 依里子(内線:7649) 先端物質科学研究科
黒木伸一郎(内線:6267) ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
- セミナー案内
Ⅲ-Ⅳ-Ⅴ族半導体デバイス 若手の会 第1回 勉強会
広島大学の半導体デバイス・プロセスの若手研究者の互いの研究の理解、研究交流、議論の場として、Ⅲ-Ⅳ-Ⅴ族半導体デバイス 若手の会 勉強会を開催いたします。第1回として、若手研究者の研究紹介(過去~現在)を行います。ご興味のある方はご参加ください。- 日時:平成25年3月15日(金) 18:00-20:30
- 場所:先端物質科学研究科 402A 会議室
- 内容:若手研究者研究紹介
- 18:00-18:05 Ⅲ-Ⅳ-Ⅴ族半導体デバイス 若手の会 趣旨説明
- 18:05-18:35 研究紹介/ 黒木伸一郎 「Low-k, TFT, そしてSiCデバイスへ」
- 18:35-19:05 研究紹介/ 花房宏明 「Ⅳ族結晶/非結晶ヘテロ接合とデバイス」
- 19:05-19:35 研究紹介/ 富永依里子 「新規III-V族半導体と光学デバイスへの応用」
- 19:35-20:05 研究紹介/ 村上秀樹 「ゲルマニウムトランジスタ実現のためのプロセス及び評価技術」
- 20:05-20:30 ディスカッション 今回は内容を広く研究紹介という形をとりますが、次回より各トピックを深堀していきます。
- 世話人:
花房 宏明(内線:7468)、富永 依里子(内線:7649) 先端物質科学研究科
黒木伸一郎(内線:6267) ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
- 第31回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
Silicon-based Thermal Sensors and Actuators for Chemical Gas Sensing Applications & Low cost polymer-based microfluidic platforms for biomedical diagnostics- 講師:Elizaveta Vereshchagina Ph.D.
(Dublin City University 研究員) - 日時:平成24年11月7日(水) 16:30-18:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 担当:三宅教授
- 講師:Elizaveta Vereshchagina Ph.D.
- 平成23年度第4回「卒業生を通じた社会交流事業」講演会
昨日まで世界になかったものを- 講師:升井 義博 氏
旭化成エレクトロニクス株式会社設計開発センター
センサーユニット センサー第一グループ
(平成21年3月 広島大学大学院先端物質科学研究科 半導体集積科学専攻 博士課程後期修了) - 日時:平成24年10月16日(金)15:30-17:00(予定)
*講演後、講師を交えた意見交換会を予定しております。(17:00-18:00) - 場所:401N講義室(先端物質科学研究科4階)
*意見交換会は5階実験棟ラウンジにて - 対象:全専攻の学生、各研究室の学部学生、教職員
- 趣旨:社会で活躍しておられる卒業・修了生を講師としてお招きし,講演並びに意見交換を通して,社会人から大学および修了生に何を期待されているかを認識し,今後の教育・研究に役立てることを目的としています。
※ 職業教育特別講義の対象科目となります。
博士課程前期学生は,「卒業生を通した社会交流事業」講演会に,在学期間を通じて6回以上出席した場合に,職業教育特別講義(選択科目)として1単位認定されます。1講演ごとに「職業教育特別講義用受講届」に受付印を受け,6回分そろいましたら,指導教員承認の上,先端物質科学研究科学生支援室へ提出してください。 - 主催:先端物質科学研究科
- 世話人:半導体集積科学専攻 藤島 実 教授
- 講師:升井 義博 氏
- 第30回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
技術の事業化プロセスと実現へ向けてのアプローチ- 講師:加藤 謙介 先生
((株)エフェクテック戦略研究所代表取締役 東京大学大学院新領域創成科学研究科非常勤講師) - 日時:平成24年3月16日(金) 15:00-16:15
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 講演概要: 先進技術の事業化へ向けたアプローチについて、基礎的な概念と共に、その実現に 必要な下記二つの考え方を紹介します。
(1)事業化のプロセス連鎖
開発技術を製品に適用させるまでのプロセスだけでなく、具体的なユーザーの取り 込みを含めた「事業化のプロセス連鎖」、さらに「事業間プロセスの価値連鎖」まで を設計することが、「技術の産業化」の推進に大きな効果を与えます。
(2)技術の適用経路の設定
期待された新しい用途市場は必ずしも順調に立ち上がるとは限らず、これに 固執すると事業上の進展は膠着する場合があります。こうした状況では、複数の 可能性に対するアプローチと阻害要因の構造化を通じて、技術の適用経路を 設定することが事業化を実現する上で重要な施策となります。
- 講師:加藤 謙介 先生
- 平成23年度第4回「卒業生を通じた社会交流事業」講演会
京速コンピュータ「京」(*1)とSPARC64(TM)VIIIfxプロセッサの開発
(*1)「京」は、理化学研究所が2010年7月に決定した「次世代スーパーコンピュータ」の愛称です。- 講師:岡野 廣 氏
(株式会社富士通研究所プラットフォームテクノロジー研究所デザインソリューション研究部主任研究員と富士通株式会社 次世代テクニカルコンピューティング開発本部 LSI開発統括部 第一技術部 マネージャーを兼務) - 日時:平成24年1月27日(金) 15:00-16:30
講演終了後、講師を交えた意見交換会を予定しています。 - 場所:401N講義室(先端物質科学研究科4階)
- 趣旨:
理化学研究所と富士通が共同開発中の京速コンピュータ「京」と、 そのキーデバイスである「SPARC64(TM)VIIIfx」プロセッサについて紹介します。ビデオ上映を交えて「京」の概要を説明し、筆者が開発に携わった「SPARC64(TM)VIIIfx」の高性能、高信頼、および省電力という特徴について解説します。最後に、一卒業生として、在学のみなさんへのメッセージも添える予定です。
- 講師:岡野 廣 氏

- 第29回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
ミリ波用RF・アナログCMOS集積回路設計技術- 講師:松澤 昭 先生
(東京工業大学大学院 理工学研究科電子物理工学専攻 教授) - 日時:2012年1月10日(火) 14:00-15:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 講師:松澤 昭 先生
- 第28回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
Sパラメータ入門- 講師:天川修平 先生
(広島大学 先端物質科学研究科 准教授) - 日時:2011年12月22日(木) 16:00-17:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 講師:天川修平 先生
- 講演会
My experiences in Microtechnology and Biomedical Science- 講師:Dr. Wesley Chang
(UCSF and Aperys LLC.) - 日時:2011年12月19日(月) 15:00-16:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 連絡先:石川
- 講師:Dr. Wesley Chang
- 講演会
微細化によるLSIの信頼性諸問題とその解決策 - 講師:京都工芸繊維大学工芸科学研究科電子システム工学専攻教授 小林和淑先生
- 日時:2011年11月22日(火)16:15-17:15
- 場所:先端物質科学研究科4階401N講義室
- 内容:
LSIの微細化はムーアの法則に従い着々と進行している. 本講演では, 微細化したLSIが抱える経年劣化, 一時故障, ばらつきなどの信頼性関連の諸問題とその対応策について述べる.
- 第27回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
バイオセンサ技術 - 講師:東京医科歯科大学生体材料研究所 教授 宮原裕二
- 日時:2011年11月17日(金)14:30-16:00
- 場所:先端物質科学研究科4階402N講義室
- 内容:
半導体技術と生体検出技術の融合であるバイオトランジスタの概要とその応用などについて講演いただく - 問い合わせ先:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 三宅 亮
- 講演会
磁気微粒子とホールセンサのデジタルヘルスケア応用/MEMS技術による電磁式および静電式振動型エナジーハーベスタ - 日時:2011年10月29日(金)15:15-16:50
- 場所:RNBS東棟5F会議室
- 内容:
講演1 15:15~15:55
『磁気微粒子とホールセンサのデジタルヘルスケア応用』
ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 石川智弘先生
講演2 16:00~16:50
『MEMS技術による電磁式および静電式振動型エナジーハーベスタ』
兵庫県立大学 電気系工学専攻 藤田孝之先生 - 備考:本講演は、電気学会E部門 デジタルヘルスケア時代の血糖値センサ調査専門委員会の会合を兼ねております。
- 半導体集積科学専攻講演会
組込み向けマルチコア技術の進展/LSIからみたノーマリオフコンピューティング/LEAPにおける超低電圧デバイス研究と、ばらつきが小さく基板バイアス制御が可能なSOTB(Silicon on Buried Oxide)技術 - 日時:2011年10月26日(水)10:00-12:00
- 場所:先端研401N講義室 (先端物質科学研究科4F)
- プログラム:
- 組込み向けマルチコア技術の進展
内山 邦男氏(日立製作所) - LSIからみたノーマリオフコンピューティング
小高 雅則氏(日立製作所) - LEAPにおける超低電圧デバイス研究と、ばらつきが小さく基板バイアス制御が可能なSOTB(Silicon on Buried Oxide)技術
杉井 信之氏(超低電圧デバイス技術研究組合)
- 組込み向けマルチコア技術の進展
- お問い合わせ先:半導体集積専攻 藤島 実 教授
- 第26回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
Nitride Semiconductor Nanostructures for Electronics and Optoelectornics - 講師:Prof. K. Baskar
Anna University, Chennai, India - 日時:2011年10月17日(月)13:30-14:30
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所5F会議室
- 内容:青色発光で注目されているGaNナノ構造の作製とデバイス応用、バイオセンサ応用に関する講演です。講演は英語で行われます。(This seminar will be done in English.)
- 世話人:横山 新
- 第25回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
ナノインデンテーションによる薄膜弾性率・硬さ測定/レーザSAWによる薄膜弾性率測定- 講師:清野豊先生/服部浩一郎先生
(独)産業技術総合研究所 計測標準研究部門 音響振動科 強度振動標準 研究室 - 日時:平成23年7月28日(木) 13:00-14:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 講師:清野豊先生/服部浩一郎先生
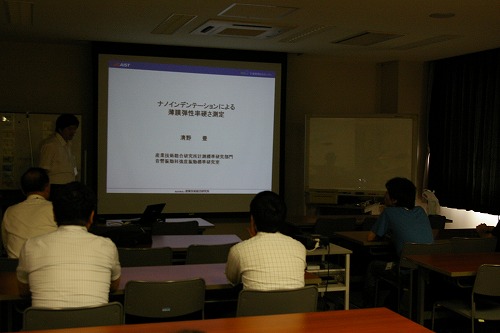

- 工学研究院セミナー
超並列メモリエンベディッドSIMD型プロセッサアーキテクチャ
- 講師:小出哲士先生
(ナノデバイス・バイオ融合科学研究所准教授) - 日時:平成23年7月8日(金) 17:00~(1時間程度)
- 場所:C1-112 (第二類会議室)
- 内容:
マルチメディア環境の発展により,モバイル機器搭載用LSIには,ユーザニーズ を満たすための高速処理,仕様の変化に柔軟に対応できるプログラマブル性, 及び実装に適した高速性,小面積,低消費電力が求められている. 一般に,マルチメディアアプリケーションは繰り返し演算処理とテーブルルック アップ処理から構成されるが,従来DSP等のLSIアーキテクチャはこれらの両方の 処理を効率よく処理することが困難であった. 本研究では,2,048個のPE (Processing Element)を有する,超並列SIMD型演算 アーキテクチャと,一致検索処理を高速に実現することのできる機能メモリである CAM (Content Addressable memory)を融合させることで,高速,小面積,低消 費電力,かつプログラマブルに様々なアプリケーションを処理することができるLSI について述べる.また,JPEG圧縮や顔検出アプリケーション等に対して適用し, その有効性について報告する.
- 講師:小出哲士先生
- 第24回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
信号処理プロセッサーにおけるワイヤライン
“Tutorial on Wireline Applications in Processors”
VLSI Symposium paper“Bridging Design and Manufacture of Analog/Mixed- Signal Circuits in Advanced CMOS”- 講師:Alvin Loke Ph.D.
(Advanced Micro Devices, Principal Member of Technical Staff) - 日時:平成23年6月17日(金) 14:00-15:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 講師:Alvin Loke Ph.D.
- 工学研究院セミナー
スカイライン集合問合せとその応用(Skyline Set Query and Its Applications) - 講師:森本康彦先生
(広島大学大学院 工学研究院 情報工学専攻) - 日時:平成23年4月15日(金) 17:00~(1時間から1時間半)
- 場所:C1-112 (第二類会議室)
- 内容:
スカイライン問合せとは,他のオブジェクトに何らかの属性値 で劣っていないオブジェクトの集合を提示する機能で, 電子商取引サイトなどでユーザに商品の選択肢を 提示する際に,よく利用されています. 今回のセミナーでは,私の研究室で近年取り組んできた, 個人情報を保護するスカイライン問合せ機能および, その時空間情報データベースへの応用,クラウド環境での 応用について紹介します.
- 半導体集積科学専攻セミナー
電気回路学入門(集中定数回路から分布定数回路へ) - 講師:矢加部利幸先生
(国立大学法人電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報・通信工学専攻) - 日時:平成23年4月8日(金) 10:10-12:00, 14:00-16:00
- 場所:広島大学先端物質科学研究科 405N講義室(広島県東広島市鏡山1-3-1)
- 内容:
午前中は学部レベルの電気回路学を、特に正弦波定常状態解析(フェーザ法)を確り復習します。 具体的には集中定数と分布定数回路の違い、線形時間不変回路とは、フェーザ法で明確となる インピーダンス、最後にデシベルについて解説します。 午後は学部レベルで学んだことを大学院修士レベルでどのように展開していくかを「伝送工学 特論」で学ぶ内容を基に解説します。具体的には伝送線路理論入門、スミスチャートの意味する もの、散乱行列の定義と活用法、最後に高周波計測技術の重要性について、できるだけ興味を 持てるよう解説します。 午前、午後供90分から100分程度で講義し、その後質疑時間を設定します。 勿論、講義途中での割り込み質問は大歓迎です。
- 第23回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「マイクロ・ナノ科学によるMEMS技術の革新~MEMS technology innovation based on micro/nano science~」 - 講師:佐藤一雄先生
(名古屋大学 大学院工学研究科 マイクロ・ナノシステム工学専攻 教授) - 日時:平成22年12月14日(火) 14:00-15:30
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 連絡先:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 分子生命情報科学研究部門 三宅 亮

- 平成22年度第4回「卒業生を通じた社会交流事業」講演会
微細化の終焉と三次元集積化 - 講師:前田展秀様
(株式会社ディスコ営業技術本部マーケティンググループ主任 東京大学工学系研究科総合研究機構ナノ工学研究センター 研究員) - 日時:平成22年12月3日(金) 13:10-14:20
- 場所:401N講義室(先端物質科学研究科4階)
- 趣旨:
社会で活躍しておられる卒業・修了生を講師としてお招きし,講演並びに意見交換を通して,社会人から大学および修了生に何を期待されているかを認識し,今後の教育・研究に役立てることを目的としています。
Old
- 第1回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「The Making of the Smallest NMR System for Human Healthcare」 - 講師:Prof. Donhee Ham
(Research Laboratory of Electronics & Integrated Circuits, Harvard University) - 日時:平成20年6月28日(土) 13:30-14:30
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 第2回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「もの作りにおける計算科学シミュレーションの役割とミクロ分野への期待」 - 講師:佐々木 直哉 様
(日立製作所機械研究所 主管研究長) - 日時:平成20年7月1日(火) 10:30-12:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 内容:
日立製作所研究開発本部内の横断的組織である高度設計シミュレーションセンタを統括されておられる佐々木直哉様は、 日立内におけるシミュレーション技術全般に精通されています。今回は、もの作りへの寄与という観点から、日立における解析・ シミュレーション技術全般について紹介を頂くとともに、SBIプロジェクトのテーマとも関連が深い材料開発、バイオ応用などへの 取り組みについても講演して頂きます。
- 第3回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「RTN: ランダムテレグラフノイズについて」 - 講師:久本 大 様
(日立製作所 中央研究所) - 日時:平成20年7月31日(木) 11:00-12:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 内容:
ランダムテレグラフノイズはソフトエラー同様、永久破壊、性能劣化では無い動作不良を 引き起こす厄介なもので、微細化に伴い深刻度が増しつつあります。そこで、今回は、この問題に関して著名な 日立製作所中央研究所 久本 大様にご講演して頂きます。なお、本講演は先端研の講義の集積システム信頼性 の一環として実施するものです。
- 第4回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「バイオセンサ技術」 - 講師:宮原 裕二 先生
(独立行政法人 物質・材料研究機構生体材料センター センター長、
東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻教授、
広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所客員教授) - 日時:平成20年11月13日(木) 14:30-16:30
- 場所:先端科学総合研究棟402N
- 内容:
宮原先生は、電界効果トランジスタ(FET:field effect transistor)を用いた 化学・バイオセンサの日本における草分け的存在です。
本講義では、まずバイオセンサ技術の基本・概要について説明頂き、 次に最近の成果であるバイオ・トランジスタ技術 (分子電荷を直接検出する新しい方式の一塩基多型(SNPs)解析、DNAシーケンシング技術、細胞トランジスタなど) について紹介頂きます。 また最後にエレクトロニクスとバイオ・医療の接点を探るとともに,その将来を展望して頂きます。
- 第5回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「XOI基板を用いた集積化技術」 - 講師:
- イントロダクション: SOI、GeOI、III-VOI の流れ
芝原 健太郎 (広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 准教授) - 高熱伝導性Si-on-SiC基板の製作とシリコンMOSFETへの応用
吉本昌広 先生 (京都工芸繊維大学 教授)
- イントロダクション: SOI、GeOI、III-VOI の流れ
- 日時:平成21年1月15日(木) 16:20-17:20
- 場所:先端科学総合研究棟402N
- 内容:
SiCは、ワイドギャップ半導体として知られているが、 それに加えてシリコンの約3倍の熱伝導率を有する材料である。 このため、SiCを絶縁基板とするSOI基板上にデバイスを製作することで、 デバイスから発生する熱を効率的に逃がすことができ、 よりハイパワー、高温下での動作が期待できる。 また、従来のSOI構造に加えて、SiCの導電性制御により、 良好な熱伝導と電気伝導を兼ね備えた基板構造も実現できる。 本講演では、Si-on-SiC基板の製作について紹介したのち、 同SOI基板上に製作したシリコンMOSFETの特性をもとに、 同SOI基板の放熱効果について述べる。
- 第6回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「表面プラズモン共鳴バイオセンサーによる細胞応答の検出と臨床応用」 - 講師:秀 道広
(広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 教授、
広島大学 大学院医歯薬学総合研究科 皮膚科学 教授、
広島大学 医学部医学科 学士課程教務委員長) - 日時:平成21年2月3日(火) 17:00-18:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 内容:
秀先生は医学の先生ですが、応用物理学会の春季講演会で招待講演をされるなど応用物理に造詣が深く、 実際に表面プラズモン共鳴バイオセンサーデバイスの研究をしておられます。学生諸君も異分野の先生による デバイス物理応用について是非傾聴してください。
- 第7回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「0.5V駆動LSI実現に向けた極低消費電力電圧制御発振器」 - 講師:岡田 健一先生
(東京工業大学 大学院理工学研究科 電子物理工学専攻准教授) - 日時:平成21年10月13日(火) 14:00-15:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 第8回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「Cyborg Beetle Project」 - 講師:Dr. Hirotaka SATO
(UC Berkeley, Berkeley Sensor and Actuator Center) - 日時:平成21年11月11日(水) 14:00-15:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 内容:
カブトムシやハナムグリといった甲虫類は、体重比で大きなペイロードを持たせても飛行でき、神経節への単調な 刺激のみで飛翔を続ける、という特徴を有する。神経節に接続されたチップを体内または体表に持ち、無線信号 により制御れた飛行を行う甲虫について、実際の実験映像を交えて紹介する。
- 第9回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「バイオトランジスタ表面の化学修飾と機能化」 - 講師:宮原裕二先生
(独立行政法人物質・材料研究機構 生体材料センターセンター長) - 日時:平成21年11月26日(木) 12:50-14:20
- 場所:広島大学先端物質科学研究科N401講義室
- 第10回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「ゲートラスト先端CMOS デバイス開発」 - 講師:若林整(ひとし)様
(ソニー(株)コンスーマープロダクツ&デバイスグループ半導体事業本部セミコンダクタテクノロジー開発部門 デバイス技術部(兼) 技術マネジメント推進室 Distinguished Researcher ) - 日時:平成22年2月4日(木) 15:15-16:15
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 内容:
ゲートラスト構造は世界で唯一high-k/metal gate デバイスを量産化しているIntel が採用している構造です。 TSMC もSOC 向けにこれを採用することを決定するなど他社にも広まりつつあるものです。しかし、これまでのポリ シリコンベースセルフアラインソース・ドレイン形成のデバイスとは異なったノウハウが使いこなしには必要になります。 若林さんにはSONYにおけるゲートラストデバイスの開発と共に、世界動向を解説していただきます。
連絡先:芝原 健太郎 (ksshiba @ hiroshima-u.ac.jp)
- 第11回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「100Gbpsを目指すミリ波/テラヘルツCMOS回路」 - 講師:藤島 実
(広島大学大学院先端物質科学研究科 半導体集積科学専攻) - 日時:平成22年2月17日(水) 16:00-17:30 (含ディスカッション30分程度)
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 内容:
ハイビジョンの無線伝送に使われる60GHz帯を中心としたミリ波CMOS回路が注目されているが、さらに周波数のたかい100GH (0.1THz)以上のテラヘルツ領域を使った無線通信の研究も始まっている。この講演では、ミリ波~テラヘルツCMOS回路の我々 の取り組みと研究動向について報告する。
- 第12回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「超並列計測によるRF電界の映像観察」 - 講師:土屋 昌弘先生
(情報通信研究機構・上席研究員) - 日時:平成22年2月18日(木) 13:30-14:30
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 内容:
光学的周波数変換技術とCMOSイメージセンサの組合せによりRF計測の超並列化が可能である。この原理を利用した RF電界映像化技術は電界カメラ(http://lei-camera.nict.go.jp/)と呼ばれ、信号伝搬の空間情報を映像としてその場 観察する機能を提供する。ここでは、電界カメラの原理と応用について概説する。
- 第13回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
- 日時:平成22年2月24日 13:30-15:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- スケジュール:
- 13:25-13:30 講師の先生方のご紹介
- 13:30-14:00 「スルーチップインタフェース」 講師:黒田忠弘先生(慶応義塾大学教授)
- 14:00-14:30 「フレキシブルエレクトロニクス」 講師:染谷隆夫先生(東京大学教授)
- 14:30-15:00 「超低電圧動作による低エネルギーLSI」 講師:高宮真先生(東京大学 准教授)
- 第14回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「MESOSCALE CHEMICAL SYSTEMS
-microfluidics and nanotechnology for (bio)chemical synthesis and analysis-」 - 講師:Prof. J.G.E. Han Gardeniers
(Mesoscale Chemical Systems MESA+ Institute for Nanotechnology University of Twente (オランダ)) - 日時:平成22年3月4日(木) 16:00-17:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 第15回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
- 日時:平成22年3月9日 13:00-16:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- スケジュール:
- 13:00-13:50 「π計算世界新記録樹立の表裏」
講師:金田康正先生(東京大学情報基盤センター) - 14:00-14:50 「RP-X: A 45nm 37.3GOPS/W Heterogeneous Multi-core SoC」
講師:荒川文男先生(ルネサステクノロジ) - 15:00-15:50 「低電力メモリ技術の動向」
講師:竹内健先生(東京大学工学系研究科)
連絡先:石川智弘 (ishikawa @ hiroshima-u.ac.jp)
- 13:00-13:50 「π計算世界新記録樹立の表裏」
- 第16回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「ナノ粒子材料の合成・機能化と電子および医療分野への応用展開」 - 講師:奥山喜久夫
(広島大学工学研究科 教授) - 日時:平成22年3月11日(木) 13:30-15:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 第17回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「新しい有機半導体材料の開発と薄膜トランジスタへの応用」 - 講師:瀧宮 和男
(広島大学工学研究科 教授) - 日時:平成22年4月21日(水) 15:00-16:15
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 内容:
安定性と特性を両立させるための分子設計指針に基づき,演者のグループにおいて開発された新しい有機半導体材料の性質 と薄膜トランジスタにおける特性について紹介する。
- 第18回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「ケイ素元素の特徴を活かした有機材料開発」 - 講師:大下 浄治
(広島大学工学研究科 教授) - 日時:平成22年5月12日(水) 16:30-17:30
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 第19回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「Dropletを用いるマイクロ流体操作 」 - 講師:火原 彰秀(ひばら あきひで)先生
(東京大学生産技術研究所 准教授) - 日時:平成22年5月17日(月) 15:00-16:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 第20回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「マイクロ・拡張ナノ流体デバイス工学と化学・バイオへの展開」 - 講師:北森武彦 先生
(東京大学大学院工学系研究科 教授, 研究科長,
同 大学院工学系研究科応用化学専攻) - 日時:平成22年6月16日(水) 17:00-18:00
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 第21回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「企業における技術経営~技術を事業に昇華させるたゆまざる努力と挫折、そして僅かな成功~」 - 講師:大木 博 様
((株)日立ハイテクノロジーズ コーポレート技師長 広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 客員教授) - 日時:平成22年9月30日(水) 15:30-16:30
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 連絡先:三宅
- 内容:
生き物と同じように、事業には「生」があれば必ず「死」がある。「技術」を経営 資源として事業を推進している先端企業では、「技術経営」が非常に重要であ る。大学や世の中で誕生した、事業化の可能性を秘めた「技術の芽」を敏感に察知 し、それを「目利き」して自社に取り込む、幾多の試練を乗り越えて忍耐強く「事 業として立ち上げる」、これらの段階が技術経営で一番難しく、かつ面白いところ である。これら一連の活動は「技術を事業に『昇華』させる」作業に他ならない。 夢と苦難の黎明期を経て、希望と栄光の成長期を謳歌し、やがて飽和・衰退期を迎 えて、事業は一生を終える。雇用を拡大し、社会に貢献し、社員ひとりひとりに遣 り甲斐をもって働いてもらうためには、企業は常に自社の事業を新陳代謝させなけ ればならない。現在の主力事業に注力する一方、常に新たな事業を探索し挑戦する ことが経営の最重要課題である。幾つかの実例を交えて、弊社の技術経営の一端を ご紹介する。 科学技術創造の最前線にいる先生方のご意見、コメントなどを頂戴できれば幸いで ある。
- 第22回ナノデバイス・バイオ融合科学研究所セミナー
「結晶シリコン太陽電池製造技術と、ECNの成長戦略」 - 講師:小松 雄爾 様
(オランダ ECN Solar Energy, Silicon PV, Material and Processingグループリーダ) - 日時:平成22年10月4日(月)13:30-14:45
- 場所:ナノデバイス・バイオ融合科学研究所東棟5F会議室
- 内容:
ニュースで目にする太陽電池の生産量は、なぜワット単位なのか。同じ 半導体素子でありながら、マイクロ・ナノデバイスとは全く製造方法の 異なる太陽電池の製造プロセスをお話します。また、これから20年、40 年後に、どれだけの太陽電池の製造が必要とされているのか、そのため の製造技術開発はどのようにすべきなのかを、ECNの成長戦略とあわせ てご紹介します。質疑時間では、最初に挙げたような素朴な疑問に、わ かりやすくお答えできたらと思います。また、オランダの公営研究所 ECNに勤務していますので、海外に転職して働くこと自体などについて も、どうぞ自由にご質問ください。
旧ナノデバイス・システム研究センター時代の講演会情報は こちら.